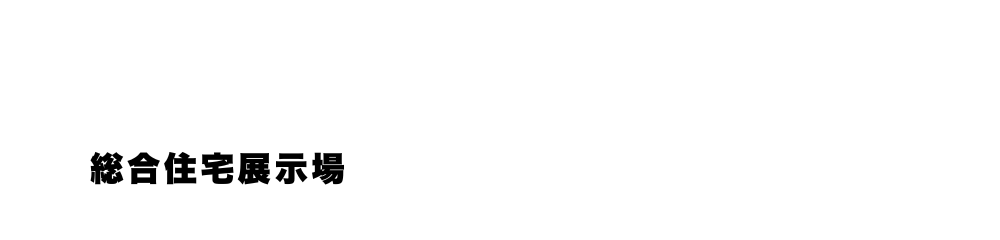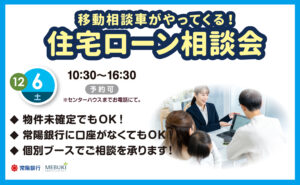新築のコンセント配置で失敗しない!実際に住んで分かった「後悔ゼロ」の設計術17のポイント #column
この記事を読めば分かること
この記事では、新築住宅を建てる際のコンセント配置について、以下のことが詳しく分かります。
- 各部屋に必要なコンセントの数と最適な配置場所
- キッチン、リビング、寝室など場所別の具体的な設置ポイント
- 実際に住んでみて分かった失敗例と成功例
- コンセントの高さや位置による見た目のスッキリ度の違い
- 家具で隠れないための事前チェック方法
- 建てる前に確認すべき電化製品リストの作り方
はじめに
「コンセントなんて、適当に付けておけば大丈夫でしょ」
マイホームの間取りを決める打ち合わせ中、夫がそう言い放った瞬間、私の背筋に冷たいものが走りました。リビングの壁紙、キッチンの高さ、お風呂の広さ…決めることが山のようにある家づくり。確かにコンセントは地味な存在です。でも、毎日使うものだからこそ、その「地味さ」が後悔の種になるんです。
実際に家を建てて住み始めてから3年。朝、スマホを充電しながらドライヤーを使い、夜はベッドサイドでタブレットを見ながら間接照明をつける…そんな何気ない日常の中で、「あのとき、もっと真剣にコンセントの位置を考えておけば」と思う瞬間が何度もありました。
逆に、「ここにコンセントを付けておいて正解だった!」と毎日感謝している場所もあります。その差は、ほんの少しのイメージトレーニングができたかどうか。建てる前に、あなたの暮らしを具体的に想像できたかどうかなんです。
この記事では、実際に注文住宅を建てた経験から学んだ、コンセント配置の「後悔ポイント」と「成功ポイント」を、あなたにお伝えします。中学生のあなたも、これから家を建てるご家族の方も、一緒に「住みやすい家」について考えてみませんか。
充電する場所を「見える化」すれば失敗しない
夜10時、リビングのソファに座ると、いつもの光景が広がります。コーヒーテーブルの上にはスマホ、タブレット、ワイヤレスイヤホンのケース、そして充電ケーブルが絡まり合っている…。もしあなたの家もこんな状態なら、要注意です。
なぜ充電場所が大切なのか?
現代の生活で、充電が必要な機器は驚くほど増えています。スマホ、タブレット、ノートパソコン、ワイヤレスイヤホン、電動歯ブラシ、電気シェーバー、スマートウォッチ、ワイヤレスマウス…数えてみると、一人あたり5〜10個もの充電機器を持っていることも珍しくありません。
家族4人なら、単純計算で20〜40個。これらの「充電場所」を決めずに家を建てると、どうなるでしょう?
リビングのテーブルはケーブルだらけ、洗面所では充電器の取り合い、寝室では延長コードがベッドまで這っている…想像しただけでストレスですよね。
実践!充電マップを作ってみよう
家を建てる前に、ぜひやってほしいことがあります。それは「充電マップ」作り。難しいことではありません。紙とペンを用意して、次の3つを書き出すだけです。
- 家族全員が持っている充電機器をリストアップ
- 「どこで充電したいか」を決める
- その場所にコンセントが何口必要か計算する
例えば、玄関近くに「お帰り充電ステーション」を作るという発想。帰宅したらすぐにスマホを置いて充電できれば、リビングがケーブルだらけになりません。寝室の枕元には、スマホとスマートウォッチ用に2口。洗面所には、電動歯ブラシとシェーバー用に別々のコンセントを。
「そんな細かく決めるの?」と思うかもしれません。でも、この手間を惜しむと、住み始めてから毎日不便を感じることになるんです。
毎日の動線を映画のように想像する
朝7時、アラームが鳴ります。あなたは寝室から起き上がり、洗面所へ向かいます。歯を磨きながら電動歯ブラシを手に取る…このとき、充電器を外す必要がありますか?それとも別のコンセントでドライヤーを使えますか?
次にキッチンへ。コーヒーメーカーのスイッチを入れ、トースターでパンを焼く。炊飯器の保温ランプが点いている。電気ケトルでお湯を沸かす…この4つが同時に使えるだけのコンセントがありますか?
動線チェックの魔法
家づくりのプロが教えてくれた秘訣があります。それは「一日の暮らしを、映画のように頭の中で再生してみる」こと。
朝起きてから夜寝るまで、あなたが家の中でどう動くのか。どこで何をするのか。どの電化製品を使うのか。まるで自分が主人公の映画を見るように、具体的にイメージするんです。
すると見えてくるのは、「階段掃除のときにコードが届かない」「ソファに座ったまま充電できない」といった小さな不便。これらは図面を眺めているだけでは絶対に気づけません。
掃除機問題を侮るなかれ
意外と盲点なのが掃除機のコンセント。特に階段です。1階から2階まで掃除機をかけるとき、コードは届きますか?コードレス掃除機なら問題ありませんが、コード式を使うなら要チェック。
友人の家では、階段の掃除をするたびに、1階と2階の両方からコードを引っ張る必要があり、毎回ストレスを感じているそうです。「たかが掃除機、されど掃除機」。週に何度も使うものだからこそ、配置には気を配りたいですね。
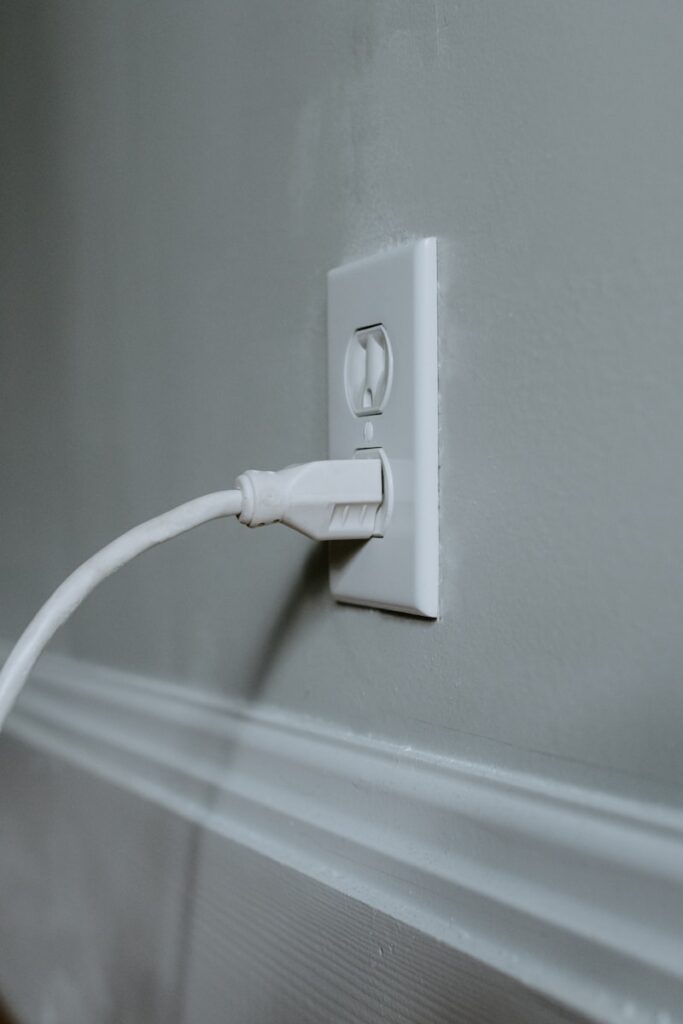
キッチンこそ「未来の自分」を想像せよ
キッチンに立つと、目の前には炊飯器、電気ケトル、トースター、コーヒーメーカー。カップボードの下には、ミキサーとフードプロセッサー。これが今の我が家の定番メンバーです。
でも、3年前に家を建てたとき、ホームベーカリーを買うなんて思ってもいませんでした。オーブンレンジを新調することも、食洗機を導入することも。
「今」だけじゃなく「5年後」を見る
キッチンのコンセント配置で最も大切なのは、「余裕を持つこと」。今使っている家電だけで計算すると、確実に足りなくなります。
なぜなら、キッチン家電は増える一方だから。便利な調理家電が次々と登場し、「これ欲しい!」となったとき、コンセントがないと使えません。延長コードを引き回すのは見た目も悪いし、何より危険です。
私の友人は、新築のキッチンにコンセントを4口しか付けませんでした。「今使ってるのは炊飯器とトースターだけだから十分」と思ったそうです。でも2年後、電気圧力鍋を買い、コーヒーメーカーを買い、ハンドブレンダーを買い…気づけば延長コードだらけに。
隠すコンセント、見せないコンセント
もう一つの重要ポイントが「高さ」です。これ、意外と盲点なんです。
標準的なコンセントの高さは、床から25〜30センチ。でも、カップボードの上に置く炊飯器やケトルを使う場合、コンセントが機器の上に見えてしまうことがあります。
我が家では、設計の段階でコンセントの位置を下げてもらいました。カップボードの天板から4センチの位置に設置することで、炊飯器の後ろにコンセントが隠れるように。このわずかな工夫で、見た目がぐっとスッキリします。
朝、キッチンに立ったとき、ごちゃごちゃしたコードやコンセントが目に入らない。それだけで、一日の始まりが気持ちよくなるんです。
パソコン作業は「ギリギリ」を覚悟せよ
「十分足りると思ったのに…」
リモートワークが始まって1ヶ月、私は呆然としていました。デスクの上には、ノートパソコン、外付けモニター、デスクライト、スマホの充電器、会社用のスマホ充電器、ワイヤレスイヤホンの充電器…。コンセントを6口用意したはずなのに、ギリギリだったんです。
在宅ワーク時代のコンセント事情
数年前までは、パソコンデスクに必要なコンセントは2〜3口で十分でした。でも今は違います。
オンライン会議が当たり前になり、ウェブカメラ、マイク、スピーカー、ライトなど、周辺機器が激増。子どもたちもタブレットでオンライン授業を受け、学校用のタブレットを充電し、自分用のタブレットも充電する。
家族4人がそれぞれ在宅ワークや学習をする場合、一人あたり5〜8口のコンセントが必要になることもあります。
コードを隠す工夫が生活の質を上げる
パソコン周りでもう一つ考えたいのが「コードの目立ち方」。
我が家の夫の書斎は、壁に向かって机を配置し、コンセントは壁の低い位置に設置しました。おかげでコード類は机の下に隠れ、すっきりした印象です。
一方、私のワークスペースはリビングの一角。オープンなカウンターデスクで、後ろを振り返ればリビング全体が見渡せる開放的な場所です。便利なのですが、コード類が丸見え…。
「もう少しコンセントの位置を工夫すればよかった」と後悔しています。例えば、デスクの天板と同じ高さにコンセントを付けたり、カウンターの背面に隠したり。そんな工夫ができたはずなんです。
ソファとベッド周りには「隠れた需要」がある
日曜日の午後、あなたはソファに深く沈み込んでいます。手にはスマホ。でもバッテリーが残り10%…。充電したいけど、コンセントは3メートル先の壁。そこまで歩くのも面倒で、結局そのまま使い続ける。
こんな経験、ありませんか?
くつろぎ空間こそコンセントが必要
ソファ周りとベッド周りは、実はコンセントの需要が非常に高い場所。長時間過ごす場所だからこそ、充電したり、照明を使ったり、暖房器具を使ったりします。
我が家のソファは、リビングの窓際に配置しています。冬は寒いので、足元に小型のヒーターを置きます。読書灯も欲しい。スマホの充電もしたい。タブレットでNetflixも見たい。Bluetoothスピーカーも置きたい…。
すると、最低でも4〜5口のコンセントが必要になります。
家具で隠れる悲劇を防ぐ方法
ここで大きな落とし穴があります。それは「家具で隠れる問題」。
せっかくコンセントを付けても、ソファやチェスト、テレビ台、ベッドで隠れてしまっては意味がありません。我が家のソファも、実は後ろにコンセントが1口あるのですが、完全にソファの裏側に隠れて使えません。
これを防ぐには、家を建てる前に家具の配置を具体的に決めておくこと。図面に実際のサイズで家具を書き込んでみるんです。ソファの幅は何センチ?奥行きは?壁からどれくらい離して置く?
この作業、面倒に感じるかもしれません。でも、この手間を惜しむと、住んでから「使えないコンセント」が生まれてしまうんです。
寝室のベッド周りも同様です。サイドテーブルを置くなら、その高さに合わせてコンセントを設置する。スマホを充電しながら寝たいなら、枕元の手が届く位置に。間接照明を使いたいなら、ベッドの後ろにも。
床コンセントという選択肢
ソファやダイニングテーブルの近くには、「床埋め込み型コンセント」という選択肢もあります。床に設置するタイプで、普段は蓋を閉じておけば踏んでも大丈夫。
ホットプレートを使うとき、延長コードを引っ張ってくる必要がなく、とても便利です。小さな子どもがいる家庭では、コードに引っかかる危険も減らせます。
ダイニングテーブルは「食事だけの場所」じゃない
土曜日の朝、ダイニングテーブルにはホットプレートが乗っています。パンケーキの甘い香りが部屋中に広がり、家族みんなで朝食を楽しむ幸せな時間。
でも、コンセントが遠くて延長コードを引っ張ってきた結果、誰かが足を引っかけそうになってヒヤリ…。こんな経験、ありませんか?
多機能化するダイニングテーブル
ダイニングテーブルは、もはや「食事だけの場所」ではありません。
ホットプレートでたこ焼きパーティー、IH調理器でお鍋、電気グリルで焼肉。子どもたちはタブレットで宿題をし、大人はノートパソコンで在宅ワーク。スマホを充電しながら食事をすることも。
つまり、ダイニングテーブル周りにもコンセントは必須なんです。
設置場所の3つの選択肢
ダイニングのコンセントには、主に3つの選択肢があります。
- 壁に設置:最も一般的。テーブルから近い壁に付ける方法
- 床埋め込み式:テーブルの真下に設置。コードが短くて済む
- テーブルの高さ:テーブルと同じ高さの壁に設置。見た目がスマート
それぞれメリット・デメリットがあります。壁設置は安価で施工も簡単ですが、コードが床を這います。床埋め込みは便利ですが、テーブルの位置を変えられません。テーブル高さの壁コンセントは見た目が良いですが、設置できる壁が限られます。
我が家は壁設置タイプを選びましたが、コードに引っかからないよう、テーブルの端から最短距離になる場所を計算して設置しました。
子ども部屋は「成長」を見据えて設計する
小学3年生の娘の部屋を覗くと、充電中の機器がずらり。学校から借りているタブレット、自宅用のタブレット、電子辞書、デスクライト、ベッドの読書灯…。小学生でもこれだけの電化製品を使っているんです。
10年後を想像できるか?
子ども部屋のコンセント配置で大切なのは、「成長した姿」を想像すること。
今は小学生でも、数年後には中学生、高校生になります。机で勉強する時間が増え、パソコンを使い、スマホを持ち、音楽プレーヤーを充電する。友達が遊びに来たときに、みんなでゲーム機を使うかもしれません。
だから、子ども部屋には余裕を持ってコンセントを設置すべきなんです。
家具配置の2パターンを考える
子ども部屋は、家具の配置が比較的予測しやすい部屋でもあります。ベッド、勉強机、本棚、クローゼット…必要な家具は大体決まっています。
おすすめなのは、家具配置の「2パターン」を考えること。
パターンA:窓際に机、壁際にベッド パターンB:窓際にベッド、壁際に机
どちらのパターンでも使いやすいように、複数の壁にコンセントを分散させておくんです。子どもの成長や好みに合わせて模様替えできる柔軟性が生まれます。
我が家の失敗は、このイメージトレーニングが不十分だったこと。娘の部屋のコンセントは、なぜかちょうど机の裏側に来てしまい、コードの存在感が気になっています。
中学生になると電力消費が倍増する
中学生の息子を持つ友人から聞いた話です。中学生になると、電化製品が一気に増えるそうです。
スマホ、タブレット、パソコン、ゲーム機、音楽プレーヤー、スマートスピーカー、デスクライト、ベッドライト…。部屋にいる時間も長くなり、夜遅くまで勉強したり、オンラインで友達と話したり。
「小学生の頃に考えていたより、ずっとコンセントが必要になった」と友人は言っていました。だから、子ども部屋には「多すぎるかな?」と思うくらいコンセントを付けておいて正解なんです。
インターネット機器は「見えない収納」に
リビングの片隅に、Wi-Fiルーターとモデムが無造作に置かれている家を見たことはありませんか?点滅するランプ、絡まったコード…。せっかくおしゃれなインテリアにしても、これでは台無しです。
機器もコードも隠してしまおう
インターネット機器は、できれば「見えない場所」に設置するのがベスト。我が家では、寝室のクローゼットの中に専用スペースを作りました。
コンセントと配線をクローゼット内に設置し、扉を閉めれば完全に見えません。でも、家じゅうどこでもWi-Fiは問題なく使えます(ただし、広い家や鉄筋コンクリート造の場合は、中継器が必要かもしれません)。
収納内コンセントの活用法
インターネット機器以外にも、「見せたくない家電」は結構あります。
例えば、充電器だらけの充電ステーション。掃除機の充電スタンド。ルンバのホームベース。延長コード。これらを収納内に配置すれば、部屋がすっきりします。
玄関のシューズクローゼットの中にコンセントを付けておけば、電動自転車のバッテリーを室内で充電できます。パントリーの中にコンセントがあれば、使わないときのホームベーカリーをしまっておけます。
「収納内コンセント」という発想、ぜひ取り入れてみてください。
エアコンコンセントで部屋の印象が変わる
「えっ、エアコンのコンセントって、そんなに気になる?」
そう思うかもしれません。でも、エアコンのコンセントは目線の高さにあり、意外と視界に入るんです。
天井付けという選択
我が家の設計士さんが提案してくれたのが、「エアコンコンセントの天井付け」。
通常は壁に付けるコンセントを、天井に設置する方法です。すると、エアコン本体の陰にコンセントが隠れ、下から見上げてもほとんど見えません。コードも短く目立たず、部屋全体がすっきりした印象になります。
追加費用はほんのわずか。でも、見た目の満足度は大きく違います。特に、インテリアにこだわりたいリビングや寝室では、おすすめの工夫です。
アクセントクロスとコンセントの「色問題」
新築のショールームで、素敵なアクセントクロスを見つけました。深いネイビーブルーの壁紙。「これ、寝室に使いたい!」と即決。
でも、住み始めてから気づきました。白いコンセントが、ネイビーの壁でくっきり目立ってしまう…。
白いコンセントは白い壁専用
標準的なコンセントは白色です。白い壁なら目立ちませんが、色付きの壁や柄付きの壁紙に付けると、どうしても浮いて見えます。
対策は3つあります。
- コンセントの色を変える:アクセントクロスに合わせた色のコンセントプレートに交換
- 配置を工夫する:家具で隠れる位置に設置する
- デザインコンセントを選ぶ:おしゃれなデザインのものを選び、むしろ見せる
我が家は後から気づいたので、1番の方法でコンセントプレートを交換しました。ネイビーのアクセントクロスに合わせて、グレーのプレートに。これだけで、ぐっと馴染みました。
アクセントクロスは計画的に
アクセントクロスを使う壁を決めたら、その壁のコンセント位置も同時に確認しましょう。高さ、位置、数、色…すべて含めて「壁のデザイン」として考えるんです。
おしゃれな家は、こうした細部まで気を配っているから、おしゃれなんですよね。
シミュレーションは「やりすぎ」がちょうどいい
家を建てて3年。今、あの頃の自分にアドバイスできるなら、こう伝えます。
「コンセントのシミュレーションは、やりすぎくらいでちょうどいいよ」
初心者でも工夫できる唯一のポイント
家づくりには、プロの知識が必要な部分がたくさんあります。構造、断熱、配管、電気…専門的すぎて、素人には判断できないことばかり。
でも、コンセントは違います。家づくり初心者でも、自分の暮らしを具体的に想像することで、最適な配置が見えてくるんです。
「迷ったら付ける」が正解
コンセントを1口増やすのに、建てる前なら数千円で済みます。でも、建てた後に追加するのは、電気工事が必要で、数万円かかることも。
だから、迷ったら付ける。これが正解です。
「ここにコンセントあったら便利かも…でも使わないかな?」と悩んだら、付けておきましょう。使わなくても困りませんが、なくて困ることはあります。
一覧表を作ろう
最後に、実践的なアドバイスを。コンセント配置を考えるとき、次の表を作ってみてください。
- 部屋名
- 置く予定の家電製品
- 常時使うもの / 時々使うもの
- 将来買いたい家電
- 必要なコンセント数
これを全部屋分作ります。手間はかかりますが、この作業こそが「後悔しない家づくり」の第一歩なんです。
まとめ
新築住宅のコンセント配置は、一見地味なテーマ。でも、毎日の暮らしやすさを左右する、とても大切なポイントです。
この記事で伝えた17のポイント
- 充電機器の「定位置」を決めておく
- 一日の動線を映画のように想像する
- 掃除機のコードが届く範囲を確認する
- キッチンは今の2倍のコンセントを用意する
- カップボードのコンセント高さを下げる
- パソコン周りは余裕をもって5〜8口確保
- コード類を隠す工夫をする
- ソファ周りに4〜5口用意する
- 家具で隠れない位置を確認する
- ベッドサイドは手が届く高さに
- ダイニングには床埋め込みも検討
- 子ども部屋は成長を見据えて多めに
- 家具配置の2パターンを想定する
- インターネット機器は収納内に隠す
- エアコンコンセントは天井付けで
- アクセントクロスに合わせて色を選ぶ
- 迷ったら設置する
建てる前の今だからこそ、じっくり考える価値があります。あなたの新しい家が、毎日快適に暮らせる場所になりますように。コンセント配置、ぜひ楽しみながら計画してくださいね。