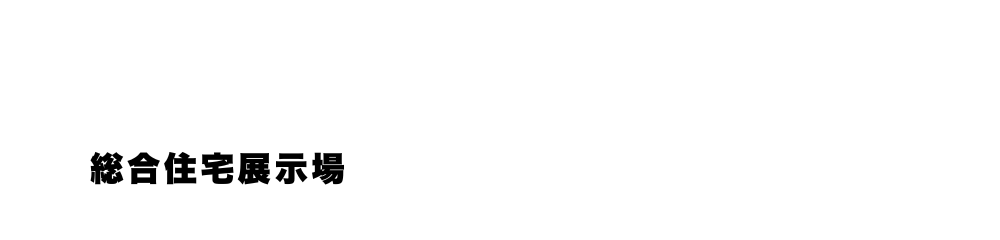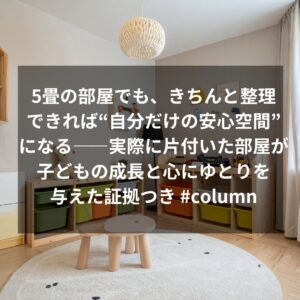毎日の料理がラクになり、見た目もすっきり美しくなる “使いやすいキッチン収納” のコツ — その根拠と具体的な方法を、整理収納の専門家が図と実例で証明します! #column
この記事を読めば分かること
この記事を読めば、キッチン収納が「なぜゴチャゴチャしやすいか」という原因から、シンク下・コンロ下・調理台下・吊戸棚それぞれの最適な収納の考え方と具体アイディアまで、すぐ実践できる方法を理解できます。あなたのキッチンが、使いやすく片づく場所へ変わるヒントがつまっています。
はじめに
料理中、あれを取り出そうと手を伸ばすと、目当てのものが見つからずもたついた経験はありませんか?
「鍋が重なって取りにくい」「調味料がバラバラ」「高い棚に届かない」——キッチンは毎日使う場所だけに、小さなストレスが積み重なりやすい空間です。
でも、ちょっとした「収納の考え方」を変えるだけで、モノが自然と定位置に収まり、料理がスムーズになり、キッチンに立つのが楽しくなる。
この記事では、キッチン収納改善の鍵を、具体的な実例を交えながら、小説のように情景を浮かべながらあなたにお伝えします。読み進めるうちに、「わが家のキッチンではこうしてみよう」と自然にアイディアが湧いてくるように書いています。
なぜキッチン収納は難しいのか? 〜片づけの道を知る〜
① モノの種類がものすごく多い ⇒ “パズルが複雑すぎる”
キッチンには、食材、調味料、キッチンツール、鍋・フライパン、食器、保存容器など、多種多様なモノがあります。
この種類の多さが、どこに何を置けばよいか迷わせてしまいます。
まるでピースがたくさんあるパズルを前にして、まず「輪郭」や「色分け」ができていないと全体像が見えないような状態です。
② 使う頻度・出し入れの回数が多い ⇒ “散らかるチャンスがいっぱい”
他の部屋と違って、キッチンは毎日使います。調理をして、後片付けをし、買い物から戻ればまた物が増える。
このように、出し入れが頻繁だからこそ、「使いやすさ」が重要になるのです。
この2つの理由を理解することが、収納を見直す第一歩です。

キッチン各エリア別収納ルールと具体アイディア
以下では、キッチンを「シンク下」「コンロ下」「調理台下」「吊戸棚」という4エリアに分け、それぞれに特化した収納のコツを紹介します。
1. シンク下:湿気と配管を避けつつ、使用頻度の高いアイテムを
シンク下は、水が流れる配管があるため、湿気が出やすく、臭いもこもりがち。
そのため「食品」は基本的には置かず、調理前後の道具や洗剤・掃除用品などを収納するのが安全です。
また、収納スペースが広いため、ラックや仕切りを使って縦・横に区画を作ると効率的です。
たとえば、ざる・ボウルを重ねないように縦置きしたり、ラックを使って立体的に収納したり。空いたスペースには資源ごみ入れを置いた例もあります。
情景描写:朝、シンク下の扉を開けると、白いラックが2段に分かれ、上段にはスポンジや洗剤、下段にはペットボトルゴミ箱がすっきり収まっている光景が目に浮かびます。
2. コンロ下:火を使う場所にふさわしい収納を
コンロ下には、調理で使う鍋・フライパン・油などを配置するのが一般的です。
でも、鍋を重ねてしまうと下にあるものが取りにくくなるので、「立てて収納」する手法が効果的です。
フライパンラックを使って、ひとつひとつを立てて収納すれば、パッと見渡せて手が届きやすくなります。
情景描写:夕飯の支度中、カチャッと引き出しを引くと、鍋が縦にずらりと並び、それぞれの取っ手をつかんで一瞬で取り出せる様子を想像してください。
3. 調理台下:見渡せて取り出しやすく、使いやすさが決め手
調理台下は、作業をしながらよく使う調理器具・道具・保存容器・調味料を置く場所です。
ここでは「上から全体が見える」収納が大切。「重ねる」のではなく「立てる」「見える化」することがポイントになります。
同じ種類の保存容器を揃えたり、ラベルを貼ったりすることで、何がどこにあるかをすぐ把握できます。
情景描写:あなたが包丁を取り、調理台下をパッと開けると、中には透明な保存容器が列をなして置かれ、ラベルがまっすぐ整っている。調味料の瓶も背をそろえて立ててある、そんなすっきりした光景。
4. 吊戸棚:重くないモノで、高さを味方に使う
吊戸棚は高い位置にあり、取り出しにくいので、軽くて使用頻度の低いものを収納するのが基本です。
乾物、お菓子のストック、保存容器、調理器具(年に数回しか使わないもの)などが適しています。
また、バラバラと小さなモノを入れてしまうと混乱を招くので、取っ手付き収納ケースや手が届きやすい持ち手付き容器を活用すると便利です。
情景描写:目線を上に移すと、吊戸棚に、取っ手付きの白いボックスが横並び。ひとつを引き出すと直射日光を浴びずに、乾物やお菓子のストックが整然と並んでいます。
なぜこの法則が効くのか? — 理由を押さえよう
各エリアごとの収納法には、それぞれ合理的な理由があります:
- 食品をシンク下に入れない → 湿気や水漏れリスクを避け、劣化を防ぐ
- 立てて収納 → どこにあるか見やすくなる、重ねて探す手間を省く
- 見える収納とラベル → 探す時間を減らし、戻しやすくする
- 使用頻度と重さで分類 → 取り出しやすさを優先し、ストレスを減らす
こうした理屈を理解して整理すれば、ただ真似するだけでなく、「なぜこれをこの場所に置くのか」をあなた自身で判断できるようになります。
あなたのキッチンを変えるステップ — 実践への道
ステップ1:モノの棚卸しをしよう
まず、キッチンにあるモノを全部出してみましょう。
「これは毎日使う」「たまに使う」「ほとんど使わない」に分けてみてください。
不要なものは処分か他の場所に移動。
ステップ2:定位置を決めよう
先ほどの考え方に沿って、「シンク下には洗剤」「コンロ下には鍋」「調理台下には道具」「吊戸棚には軽いストック類」という定位置を決めていきます。
ステップ3:収納グッズを選ぼう
ラック、仕切り、フライパン立て、取っ手付きケースなど、使いやすさを考えて収納グッズを選びます。できれば透明な素材で中身が見えるものを使うと効果的です。
ステップ4:収納して調整しよう
実際にモノを戻してみて、使い勝手を確かめてください。「取り出しにくい」「見つけにくい」と感じた場所は、少しずつ調整を加えていきます。
よくある失敗例と対処法:あなたもやりがちなミスを避けよう
失敗例1:深い引き出しに鍋を重ねて収納
→ 下の鍋がほとんど見えず、取り出し困難。
対処法:フライパン立てや鍋ラックを使い、縦置き・立てる収納に切り替えましょう。
失敗例2:吊戸棚に重いものを詰め込む
→ 出し入れが大変で、怪我の原因になることも。
対処法:吊戸棚にはあくまで軽くて年数回しか使わないものを。取っ手付きケースで引き出しやすく。
失敗例3:収納ケースがバラバラで中が見えない
→ 何がどこにあるか分からず、最初の状態に戻る悪循環。
対処法:透明ケースを使ったり、ラベルを貼ったりして「見える化」すること。
情景で感じる「あるべきキッチン」の一幕
夜、あたたかな照明の下、あなたは夕食の仕上げをしている。
引き出しを引くと、菜箸・スパチュラ・泡立て器が手の届く位置にあり、調味料は立ったままラベルが正面を向いて整っている。
鍋やフライパンは縦に並び、欲しいものがパッとつかめる。
シンク下からは洗剤とスポンジ、ゴミ袋が整然と、どこになにがあるか一目で分かる。
吊戸棚には軽い箱が並び、取り出しも苦にならない。
そんな、心地よく使えるキッチン風景が、もう手の届くところにあります。
まとめ
キッチン収納は、モノの種類が多く、使用頻度が高い場所だからこそ、「何を、どこに、どう置くか」が重要です。
この記事で紹介した、シンク下・コンロ下・調理台下・吊戸棚それぞれの収納の考え方と具体アイディアを参考にすれば、あなたのキッチンは見違えるほど使いやすく、美しく変わります。
まずはモノの棚卸しから始めて、定位置を決め、収納グッズを使って調整していきましょう。その結果、毎日の料理がもっとラクに、もっと楽しくなります。