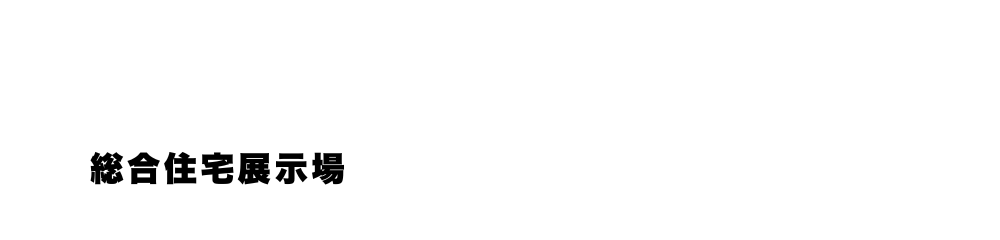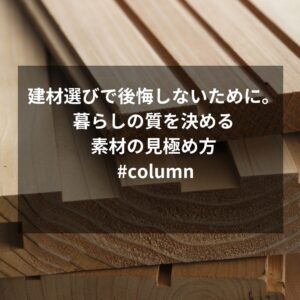暮らしを照らす、もうひとつの光。エクステリア照明で叶える安心と美しさ #column
家に帰る夜道、ふと見上げたわが家の灯りに、ほっとしたことはありませんか?
昼間は気にかけている外構も、日が暮れると暗く沈んでしまいがち。しかしエクステリア照明を上手に取り入れれば、住まいは夜でも美しく、そして安心できる場所へと変わります。
本記事では、エクステリア照明の基礎知識や種類ごとの特徴、設置ポイント、そして照明選びのコツをわかりやすく紹介します。「なんとなく明るくすればいい」ではなく、暮らしをより豊かに彩る“計算された灯り”を味方につけてみませんか?
この記事を読めばわかること
- エクステリア照明の役割と導入メリット
- 設置場所ごとの照明選びのコツ
- 照明の種類と特性
- 明るさや光色、電源タイプの選び方
- 住まいをセンスよく見せる光のテクニック
1. 外構照明がもたらす“安心感”と“豊かさ”
エクステリア照明の目的は単に「暗がりをなくすこと」だけではありません。
安全性を高める
夜間の通行で危険になりやすい段差や階段、玄関前を照らすことで、つまずきや転倒のリスクを大幅に減らせます。特に高齢者や小さなお子さんのいる家庭には欠かせません。
防犯意識を高める
暗い場所は空き巣や不審者にとって格好の侵入ポイント。人感センサー付きの照明や、死角に配置したライトが“抑止力”となります。
景観としての美しさ
光が当たることで、植栽や外壁の質感が引き立ち、昼間とは違った魅力を楽しめます。まるで夜の庭が“もうひとつのリビング”のように見えることも。
2. 設置場所に合わせた照明選び
外構のどこに照明をつけるかで、必要な明るさや光の広がり方が変わってきます。
玄関・門まわり
- 表札やインターホンを照らす門灯は来客の第一印象を左右
- センサー付き照明なら、夜間の帰宅時も安心
- フットライトを取り入れると足元も安全に
アプローチや通路
- 埋め込み型のフットライトや、低めのポールライトで自然な明るさを確保
- まっすぐ並べず、少しリズム感をつけることで景観も良好
駐車場・カーポート
- 明るめのセンサーライトで車の出し入れをサポート
- 側面の壁などに設置すれば、車体への光の反射も美しく
庭・テラス
- スポットライトで植栽やオブジェをドラマチックに照らす
- 間接照明を取り入れて、夜のガーデンを“くつろぎの場”へ
3. 照明の種類と特徴を押さえよう
それぞれの照明には得意とする役割があります。用途に応じて選びましょう。
スポットライト
- 強めの光でピンポイントに照らす
- シンボルツリーや壁面のアクセントにおすすめ
ポールライト
- 胸の高さほどの柱に取り付けるタイプ
- 通路や庭の境界など、足元を優しく照らしたい場所に
フットライト
- 地面や壁面に埋め込む照明
- 直接的なまぶしさが少なく、視認性とデザイン性を両立
センサーライト
- 人や車の動きを感知して自動点灯
- 省エネかつ防犯性も高い
門灯・表札灯
- 来客時の配慮だけでなく、家の“顔”としての役割も
- 明るすぎず、やさしい光を意識すると◎

4. 明るさ・色・電源方式をどう選ぶ?
照明の性能を活かすには、数値や仕様にも注目しておきましょう。
明るさ(ルーメン)
- 玄関ポーチ:約300〜800lm
- 足元灯:約100lm
- 駐車場:約1000lm以上
光の色(色温度)
- 暖色系(2700〜3000K):落ち着いた印象
- 昼白色(4000〜5000K):明るく爽やかな印象
電源タイプ
- 電源直結型:配線工事が必要だが安定して使用できる
- ソーラー型:配線不要で設置が手軽。ただし天候に影響されやすい
5. 光の“配置”で差がつく、夜の外構演出
せっかく照明を設置するなら、ただ並べるだけではもったいない。
陰影を活かす
- あえて「光が届かない場所」を残すことで、奥行きや立体感を演出
- 植栽やフェンスの“影”がデザインになる
高さのバランスを取る
- フットライト+スポットライトなど、上下の照明を組み合わせて立体的な印象に
配置のリズムをつける
- 同じ照明を均等に並べるより、少しずらして配置することで自然な流れが生まれます
まとめ
エクステリア照明は、単なる照明器具ではなく、“暮らしの質を上げるツール”です。
・暗がりをなくし、足元の安全性を確保
・防犯対策としての効果も◎
・昼とは違った美しさで住まいの表情が豊かに
「外構の照明は最後に考えればいい」——そんな常識を見直して、光から始める住まいづくり、はじめてみませんか?