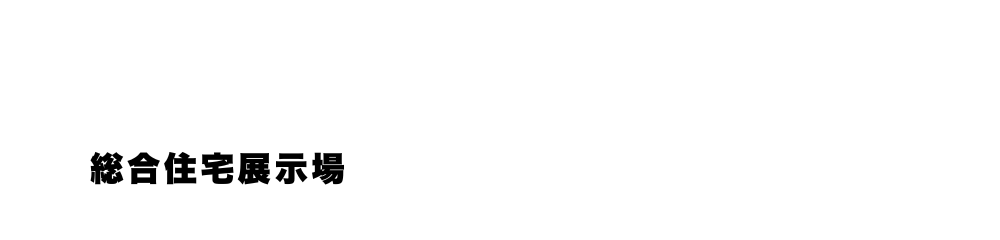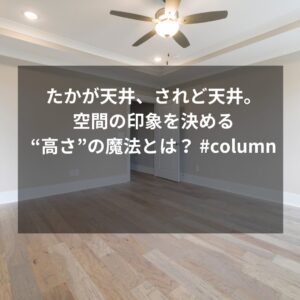家族を守る備えは“選び抜く力”から──専門家が推奨する実用的な防災グッズと住まいの工夫 #column
突然起こる地震、予測できない豪雨、停電や断水──
災害のリスクは、私たちの暮らしのすぐ隣にあります。
にもかかわらず、「防災グッズをひと通り揃えたから安心」と考えている方が多いのも事実です。しかし現場で実際に活用されたもの、逆に使われなかったものには大きな差があることをご存じでしょうか?
この記事では、防災士などの専門家による知見をもとに、「本当に必要とされる防災アイテム」や「すぐに実践できる収納術」、さらに「住宅そのものに施す防災設計の工夫」まで、実用的に解説していきます。
この記事を読めばわかること
- 必要最低限で効果的な防災グッズの選び方
- 家族構成や住環境に合わせた防災準備の考え方
- 収納性とアクセス性を両立させる保管方法
- 住宅の構造的な防災対策の具体例
- 定期点検とアップデートの重要性と実践方法
実際に役立つ防災グッズとは?「数」よりも「中身の精度」がカギ
市販の防災セットがすべて万能とは限りません。実際の災害現場では「多すぎて持ち出せなかった」「必要なものが見つからなかった」といった声が多く聞かれます。
優先順位を考慮した基本アイテム(家族1人あたり):
- 飲料水・非常食(3日分)
→ 普段食べ慣れた味でストレスを軽減 - 簡易トイレ・衛生用品
→ トイレ問題は被災初期から深刻。消臭・除菌対策も考慮 - モバイルバッテリー・ラジオ
→ 情報源の確保と安否連絡手段として必須 - ヘッドライト(懐中電灯より推奨)
→ 両手が使えることで行動範囲が広がる - 現金(特に小銭)・身分証のコピー
→ キャッシュレス不可の状況下に備える
✔ ポイント:
パッケージ商品をそのまま使用するのではなく、家族構成・地域特性を踏まえてカスタマイズする視点が重要です。

家族構成で異なる備えの中身──「わが家専用」の想定力を
一人暮らしの方と、乳幼児や高齢者を含む家庭とでは、防災グッズの中身に大きな差があります。
具体的な調整例:
- 高齢者がいる家庭
→ 常用薬、補聴器の電池、杖のスペアなど - 乳幼児がいる家庭
→ 粉ミルク、離乳食、ベビー用おしりふき、絵本やおもちゃ - 女性視点の備え
→ 生理用品、衛生的な着替え、ポンチョなどのプライバシー対策 - ペットを飼っている場合
→ 専用フード、飲料水、トイレシート、リード・キャリーケース
このように、「個別性のある備え」を可視化するためにも、家庭内で一度“防災リスト作成会議”を開くのも有効なアプローチです。
保管場所の見直しで「持ち出せる防災」に変える
防災グッズを準備していても、押し入れやクローゼットの奥深くに眠っているだけでは意味がありません。
収納の最適解とは?
- 玄関・リビング近くのわかりやすい場所
→ 一歩で手が届く位置に - 廊下や階段下など“動線上”のスペース
→ 家族全員が通る場所に保管 - 1人1個の防災リュック制
→ 年齢・体格に合わせて中身の最適化が可能
たとえば、小学生のお子さんには軽量で必要最小限の内容に絞り、高齢者にはキャリーバッグタイプを選ぶなど、“持てる設計”にすることで初動の遅れを防ぎます。
住宅自体を「備える空間」に──防災性能のある住まいの工夫
防災対策はグッズだけにとどまりません。住宅そのものに防災性能を組み込むことで、根本的な安全性が大きく向上します。
建築・設備面からのアプローチ:
- 耐震等級の見直し
→ 新築時に耐震等級2以上の設計を推奨 - 太陽光発電+蓄電池の導入
→ 災害時でも冷蔵庫・照明の稼働を確保 - 雨水タンク・貯水槽の設置
→ 飲用以外の生活用水の確保に活用 - ガラス破損対策
→ 飛散防止フィルムでケガのリスクを軽減 - 家具の固定・転倒防止策の実施
→ 地震時の二次被害防止に直結
特に注文住宅を検討している場合は、「防災配慮型住宅」の設計思想を取り入れることで、防災=コストではなく、長期的な安心への投資として合理的な判断が可能です。
防災準備は“更新されて初めて意味を持つ”
「備えたつもり」が数年後に無意味なものになっているケースは少なくありません。
定期点検のチェックリスト例:
- 半年に1回、食品・電池・薬品の期限確認
- 季節に応じて防寒具・暑さ対策グッズを入れ替え
- 子どもの成長に合わせたサイズ変更(衣類・靴など)
- 家族構成や生活スタイルの変化に合わせたリスト更新
実行しやすくする工夫としては、「家族の誕生日」や「引っ越し記念日」など、すでに覚えている日を点検日に設定すると継続しやすくなります。
まとめ
防災は、モノを「揃えること」ではなく、「選び、設計し、維持すること」です。
家族の生活スタイルや住宅環境に合わせて、防災グッズと住まいを最適化していくこと。
そして、それを“チーム”として家族で共有し、定期的に見直していくこと。
住宅展示場では、防災を意識した住宅設計や設備を実際に見て体験できます。
「万が一」を想定しながらも、ふだんの暮らしを快適に過ごすアイデアが詰まっています。防災は“備える”だけでなく、“学び、選ぶ”時代へ。
その第一歩として、展示場を訪ねてみるのも、有効なアクションのひとつです。