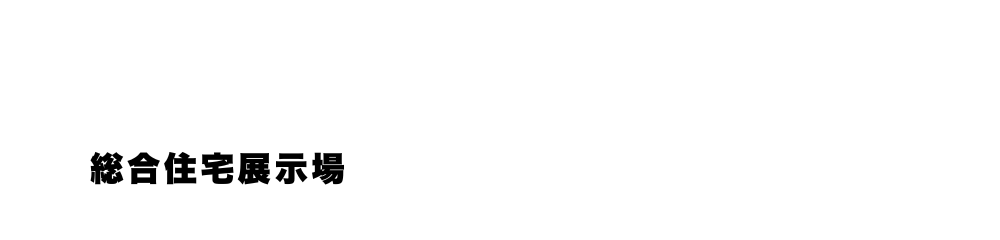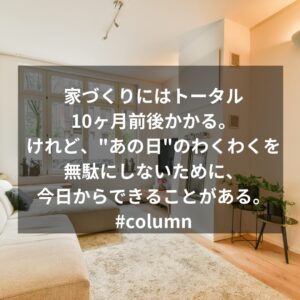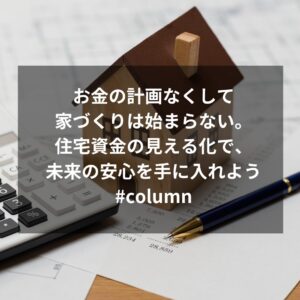たったひとつの思い込みが、あなたの夢を壊す。〜“最初の見積もり”を信じた人が、その後500万円も予算を超えたリアルな話〜#column
この記事を読めば分かること
- 注文住宅でよく起こる「予算オーバー」の正体
- なぜ想定外の出費が発生するのか、その具体的な理由
- 予算内で理想の家を建てるための実践的な考え方
- 絶対に削ってはいけない部分と、うまく削減できるポイントの見分け方
はじめに
夜、ひとりで設計図を見つめるご主人の姿。リビングのソファに深く座り込み、「本当にこれでいいのか」と静かに自問する。その傍らには、赤ペンで書き込みだらけの見積書。最初は3,000万円で建てるつもりだったはずの家が、気がつけば3,600万円。想像していた「夢のマイホーム」が、現実には不安と負債に変わっていた——。
この記事は、そんな“予算オーバーの落とし穴”にハマらないための、極めて現実的な対策をまとめたものです。
あなたが今、家づくりを真剣に考えているなら。この情報が、将来の安心と笑顔につながるはずです。
「なぜか毎回、予定より高くなる」その理由とは?
1. 見積書には含まれていない“隠れた費用”がある
注文住宅の見積書には、実はすべての費用が載っているわけではありません。たとえば「地盤改良工事」や「外構(庭・フェンス)」の費用は、後から追加されることが多いのです。
ある家族の場合、建築予定地の地盤が弱く、地盤補強工事に150万円。さらに駐車場とアプローチの外構工事に120万円。たったこの2つだけで、当初の予算から270万円もオーバーしました。
これは決して珍しいことではありません。むしろ「あるある」です。
2. ショールームで一目惚れ、グレードアップ地獄
「せっかく家を建てるならキッチンは最新式がいい」「バスルームはホテルみたいに広くてオシャレにしたい」——。
こんな気持ち、よく分かります。ただ、その“ちょっとしたこだわり”が積み重なって、結果的に予算を大幅に押し上げる原因になるのです。
ショールームで目の前にあるグレードの高い設備は、確かに魅力的です。しかし、標準仕様との差額が20万円、30万円と積もれば、最終的には数百万円の差になります。
3. 打ち合わせ中に「ついでに」追加が増えていく
打ち合わせのたびに、「収納をもう1か所増やしたい」「窓をもう少し大きくしたい」「照明をダウンライトにしたい」など、小さな変更が積み重なっていきます。
最初は5万円、次は8万円…と、感覚がマヒしてくるため、気がつけば数十万円以上の追加費用になっているケースも。
これは、建てる側と設計する側の「意思疎通のズレ」が引き起こす典型的なパターンです。
予算オーバーを防ぐための3つの視点
1. 「理想を100点で叶えよう」としない
そもそも、家づくりは“取捨選択”の連続です。100点満点の家を目指すよりも、「優先順位」を明確にし、70点で満足できるラインを見極めることが大切です。
たとえば、家事導線を優先するなら「キッチンと洗濯動線の短さ」が最優先で、外観デザインは標準でもよい、といったように考えると、コストにメリハリがつきます。

2. 「諸費用」の全体像を初期段階でリストアップする
建物本体以外の費用——たとえば、火災保険、登記費用、住宅ローン手数料、地盤調査費、外構工事などをあらかじめ把握しておくことが重要です。
「建物代だけで3,000万円」という感覚ではなく、「すべて込みで3,000万円」と逆算して予算を組むことで、後からのブレが少なくなります。
3. 「第三者の視点」で見直す時間をつくる
設計や見積りに関して、家族以外の冷静な目でアドバイスを受けるのは非常に有効です。建築士や住宅アドバイザーなどにセカンドオピニオンを求めると、見落としていたコストや、削減の余地が浮かび上がることもあります。
削ってはいけない、でも見直せるポイントとは?
削ってはいけないもの
- 断熱性能や耐震性能:暮らしの安全や快適さに直結するため、ここは絶対に妥協すべきではありません。
- 構造部分の品質:将来のメンテナンス費用に直結します。
見直す余地があるもの
- 壁紙や建具のデザイン:標準品でも十分おしゃれに仕上がる工夫はあります。
- 照明・収納の数:後付けでも対応可能なものは、必要最低限からスタートしても問題ありません。
まとめ:予算を守るのは“情報力”と“引き算の技術”
注文住宅の予算オーバーは、感覚や運の問題ではありません。それは「事前準備」と「判断力」の積み重ねです。
理想を描くことは大切ですが、現実を見据えた予算管理がなければ、家づくりは簡単に破綻します。
そして何より、あなた自身と家族が「本当に大切にしたい暮らし」を明確にすることこそが、最良のコストコントロールなのです。